もうすぐ夏も終わりですが、残暑はまだ続きそうですね。
夏と言えば、個人的に少しきついのが「汗疹(あせも)」です。
昔から汗っかきで、特に背中や胸元だけじゃなく
足の甲とかにもできちゃうんです。
でも、これまで「夏だから仕方ないか」と、何の対策もしてきませんでした。
そこで今回、改めて
「大人の汗疹って、そもそも何?」「どうすれば抑えられるの?」
という疑問を、自分なりに徹底的にリサーチしてみました!
僕と同じように、毎年の汗疹に悩んでいる方の参考になれば嬉しいです。
目次
汗疹(あせも)って、そもそも何だったの?
まず基本から。
汗疹とは、汗の通り道である汗管が詰まってしまい、
行き場を失った汗が皮膚の中に漏れ出してしまうことで起こる、
赤いブツブツや水ぶくれ、かゆみを伴う症状のことだそうです。
特に、僕たちがよく経験するかゆみを伴う赤い汗疹は
「紅色汗疹(こうしょくかんしん)」と呼ばれ、最も一般的なタイプとのこと。
大人の場合、汗をかきやすくて服と擦れる
首筋、胸元、背中、脇の下などにできやすい傾向があります。
どうして大人の僕にもできるの?原因を調べてみた
「汗疹は子供のもの」というイメージがありましたが、もちろん大人でもできます。
その原因は非常にシンプルでした。
汗疹を引き起こす主な要因は、「高温多湿な環境」と「大量の発汗」です。
汗の通り道が、垢や皮脂、ホコリなどで塞がれてしまうと、
汗がスムーズに排出されなくなります。
その状態で運動や暑さによって大量に汗をかくと、
汗が逆流して皮膚の中で炎症を起こしてしまう。
これが、あのかゆくてチクチクする汗疹の正体だったんですね。
特に、通気性の悪い合成繊維の服を着ていたり、
汗をかいたまま放置したりすると、汗管が詰まりやすくなるそうです。
【今日からできる】汗疹の予防法
原因が分かれば、対策も立てやすいですよね。
僕が「これはすぐに実践しよう!」と思った予防法を3つにまとめてみました。
1. とにかく清潔!汗をかいたら、すぐにケア
これが基本中の基本。汗をかいたら、
できるだけ早くシャワーで洗い流すのが理想的です。
それが難しい場合でも、
濡れたタオルや汗拭きシートでこまめに汗を拭き取るだけでも、
大きな予防になります。
また、洗浄料は無香料で低刺激のものを選ぶと、肌への負担が少ないようです。
2. 服装を見直す!通気性の良い衣類を選ぶ
ピタッとした服や、ポリエステルなどの合成繊維は、
熱や湿気がこもりやすくなります。
予防のためには、ゆったりとした綿素材など、
吸湿性や通気性に優れた服を選ぶのが効果的です。
僕も、残暑は意識してコットンTシャツを着ようと思いました。
3. 入浴と保湿のポイント
熱いお風呂は汗をかきすぎてしまうため、
ぬるめのシャワーや入浴で済ませるのが良いそうです。
お風呂から上がったら、ゴシゴシこすらずにタオルで優しく水分を拭き取ります。
保湿も大切ですが、汗管を塞いでしまう可能性がある
厚塗りの油性軟膏などは避けた方が良いとのことでした。
もし、できてしまったら?汗疹の対処法
予防していても、汗疹ができてしまうこともあります。
そんな時の対処法も調べてみました。
自宅でできる応急処置
まずは、冷やすことと乾燥させることが第一。
冷たいシャワーを浴びたり、タオルで包んだ保冷剤を当てたりして、
肌のほてりを鎮めましょう。
そして、掻きむしらないこと。爪を短く切っておくのも大切です。
市販薬を使う場合
かゆみや炎症が気になる場合は、薬局で相談してみるのも一つの手です。
カラミンローションや、強さの弱いステロイド外用薬(ヒドロコルチゾンなど)
が使われることがあるようです。
ただし、自己判断で長期間使い続けるのは避けた方が良いとのこと。
こんな時は皮膚科へ
数日経っても改善しない、どんどん広がる、痛いや膿を伴う、熱が出る、
といった場合は、細菌感染などを起こしている可能性もあるため、
迷わず皮膚科を受診しましょう。
まとめ:正しい知識で、残暑を快適に乗り切ろう
今回、汗疹について改めて調べてみて、
「ただの汗疹」と侮ってはいけないなと痛感しました。
でも、その原因や対策はとてもシンプルで、
日常生活のちょっとした心がけで大きく改善できることも分かりました。
正しい知識があれば、不快な汗疹はかなり防げるんですね。
僕も今日から早速、汗をかいたらこまめに拭いて、
通気性の良い服を選ぶことを徹底しようと思います!
そして汗疹ができるということは・・・
汗をかいているということ。
アラフォーなので余計
臭いとかも気になっちゃうんですよね。
なので夏は臭いケアも欠かせません
ただ、スプレーとかだとシュッシュする手間もあるので
もっといいのないかな~と探していましたが
ボディソープとか、体を洗えて臭いも抑えれて
で一石二鳥ですよね
※医療に関する注意:本記事は一般的な情報提供を目的としています。
症状が重い、長引くなど、ご自身の判断に迷う場合は、
自己判断せずに必ず皮膚科専門医にご相談ください。
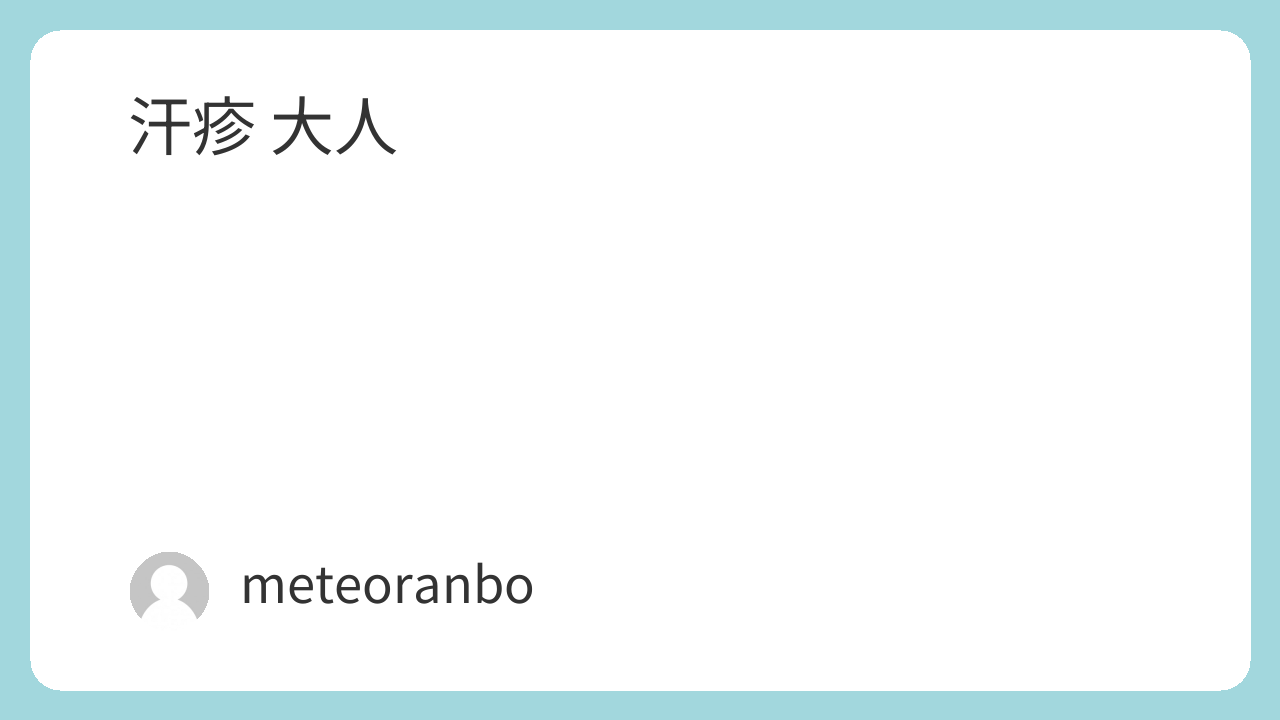
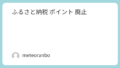

コメント